【親の死に目に会えない?】昔から伝わる「親不孝」にまつわる迷信
「親の死に目に会えない」という言葉には、親孝行できないまま親を亡くす…そんな不安や戒めが込められています。日本各地に伝わる「親の死に目」に関する迷信を、由来や背景とともに紹介します。
夜に爪を切ると親の死に目に会えない
- 最も有名な迷信のひとつ。
- 【由来①】昔は夜間に明かりが乏しく、爪切りをするとケガの危険があったため、夜に爪を切るなという教えから。
- 【由来②】江戸時代、夜間勤務を「夜詰め(よづめ)」と呼び、門番などの重要任務は親が亡くなりかけても帰宅できなかったことから「夜爪=親の死に目に会えない」と結びついた。
- 【由来③】“夜爪”は「世を詰める=寿命を縮める」に通じる忌み言葉とも言われています。
お墓や霊柩車を見ると親指を隠す
- 墓地の前を通るとき、または霊柩車や救急車を見たときに親指を隠すと「親の死に目に会える」といわれる迷信があります。
- 【由来】「親指」は“親を表す指”とされ、死や不浄から守るために隠すという考え方から来ていると言われています。
- 子どものころに自然とやっていた人も多く、「なんとなくやめられないおまじない」の一種です。
靴下を履いて寝ると親が早死にする
- これは「親が死にやすくなる」「親より先に死ぬ(=親の死に目に会えない)」という意味で忌まれた迷信です。
- もともとは「寝汗による体調不良を防ぐ」という体への配慮から来ているとも言われています。
親の死に目に会えない=親より先に死ぬ戒め
- 「親の死に目に会えない」という表現は、実は「親より先に死んでしまう不幸」を暗示する言葉でもあります。
- 生きているうちに親孝行を…という生死観と価値観が込められた伝承なのです。
【場所に宿る不思議な力】山・海・廃屋にまつわる日本の迷信
日本では古くから、特定の「場所」には神や霊が宿ると考えられ、さまざまな言い伝えや迷信が残されています。「山」「海」「廃屋」といった場所にまつわる迷信を紹介し、それぞれの背景や意味を解説します。
廃屋や古い建物に住みつく「白い蛇」
- 子どもが廃墟で遊ぶと、「蟒蛇(うわばみ)に呑まれるぞ」と叱られたという体験談も。
- 特に古い酒蔵や屋敷には白蛇が住むとされ、神聖な存在として恐れられました。
- 白蛇は金運の象徴でもありますが、子どもを遠ざけるための戒めとしても使われていたようです。
山で「おーい」と呼ばれても返事をしてはいけない
- 【迷信】山中で「おーい」と呼ばれても、その声に返すと山の神に連れていかれる。
- 【背景】実際の意味は、遭難時に山彦や他の声と区別しにくいため、別の返事をするよう教えた実用的な知恵と考えられます。
- それが民間伝承に溶け込み、神秘的な迷信として語り継がれています。
海で刃物を落とすと、神の怒りを買う
- 海の神様は金属や刃物を嫌うとされ、包丁やはさみを海に落とすと「不漁になる」と言われています。
- そのため、落としてしまった場合は木で作った模造品を神棚に供え、お詫びするという風習もありました。
海で“禁句”とされる動物:ヘビとサル
- 船の上で「ヘビ」や「サル」という言葉を口にすると、海の神の怒りに触れ不漁になると信じられてきました。
- こうした言葉の忌み言葉(禁句)は、航海安全を願う民間信仰の一種です。
海や山で亡くなった人の供養:後生車と“シルシ”
- 海で亡くなった人の遺体が見つからない場合、浜辺に“後生車”を立てて回すと、遺体が早く見つかるという迷信があります。
- どうしても見つからないときは、「故人が生前身につけていた物を代わりに埋める」という儀式が行われます。
- この行為は「シルシをヤスメル」と呼ばれ、魂を成仏させるための供養です。
【墓地の迷信】お墓参りのとき気をつけたい言い伝え
日本では、先祖を敬い、死者を大切にする文化が根付いています。そのため、お墓や霊柩車にまつわる迷信も多く伝えられてきました。墓地に関する迷信の背景や意味を、現代の視点で読み解いていきます。
親指を隠すと親を守れる?
- 【迷信】霊柩車やお墓の前を通る時は、親指を隠さないと「親の死に目に会えない」。
- 【由来】「親指」は“親を指す”とされ、死に関わるものから親を守るために隠す、という考え方が由来とされています。
- 子どもの頃に自然と身につけた人も多い、日常に根付いた迷信のひとつです。
土葬で使った草履は捨てて帰る
- 【迷信】昔の土葬では、墓を掘るときに履いた草履は、その場で捨てて帰るのが習わし。
- これは死の穢れを家に持ち帰らないための風習。
- 捨てた草履は「マムシ除けになる」とも言われ、一部地域では縁起物として拾われることもあったとか。
墓で転んだら髪を置いてくる
- 【迷信】墓地で転んだ人は「髪の毛を一本抜いて置いて帰る」とされる。
- これは「命を落とさずにすむように身代わりを置いてくる」という意味を持つとされ、恐れられていました。
- 子どもが墓で転ぶと、大人たちがそっと髪を抜こうとしたエピソードも残っています。
お墓の形にも“良し悪し”がある?
- 【迷信】猫足の墓石や、変わった形の墓(将棋の駒など)は、「成仏できない」と嫌がられることがあります。
- これは死後の世界に対する不安や慎重さの表れで、昔ながらの形状が好まれる傾向にあります。
- 特に仏教的な意味合いが強い地域では、こうした迷信が根強く残っている場合もあります。
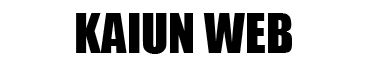






コメント