動物に宿る神性
日本には、古代から神と共に生きた「聖獣(せいじゅう)」という存在が数多く伝えられています。これらは単なる動物ではなく、神の使いや神格そのものとして、人々の信仰・祭祀・生活文化に深く根を下ろしてきました。
ここでは、神道の四神や龍、八咫烏といった神獣から、犬神・くだ狐といった民間信仰の霊獣まで、多様で奥深い「日本の聖獣」たちの世界をご紹介します。
日本の聖獣・霊獣 一覧
1. 四神(しじん)
中国由来ですが、日本の神道・陰陽道・風水にも大きく影響を与えた神聖な存在です。
- 青龍(せいりゅう)
方位: 東
象徴: 水・春
関連信仰・文化: 平安京の東を守護(鴨川=青龍) - 朱雀(すざく)
方位: 南
象徴: 火・夏
関連信仰・文化: 平安京の南(朱雀門) - 白虎(びゃっこ)
方位: 西
象徴: 金・秋
関連信仰・文化: 京都西の道「白虎通」など - 玄武(げんぶ)
方位: 北
象徴: 水・冬・長寿
関連信仰・文化: 蛇と亀の合体した神獣。北山(船岡山)に対応
➡ 平安京の守護四神思想は、実際の都市設計に取り入れられており、日本文化に深く根付いています。
2. 麒麟(きりん)
- 起源:中国の想像上の動物で、仁義・聖人の象徴。
- 日本での扱い:神聖な動物として、特に天皇の徳や平和の象徴とされることが多い。
- 神社との関係:直接祭神ではないが、神聖な存在として絵や彫刻で表現される。
3. 鳳凰(ほうおう)
- 起源:中国の霊鳥で、天子の徳と天下泰平の象徴。
- 日本での扱い:
- 平等院鳳凰堂(京都)の屋根に金の鳳凰像。
- 皇室の紋章や装飾によく使用される。
- 神道的意義:神仏混交時代においては神聖な象徴の一つ。
4. 八咫烏(やたがらす)
- 三本足の霊鳥
- 神話出典:『日本書紀』などに登場。
- 象徴:神の導き、太陽の使い(天照大神の使いとも)。
- 現代の影響:日本サッカー協会のシンボルマークにも使用。
5. 白蛇(しろへび)
- 神使であり聖獣とされることも
- 宇賀神や弁財天の象徴
- 象徴するもの:富・水・知恵・再生
- 信仰の形:白蛇を飼育している神社もある(例:岩国の白蛇神社)
6. 龍(りゅう)
- 中国由来の神獣だが、日本でも独自に信仰
- 水神、雨乞いの対象
- 有名な神社:箱根神社、貴船神社など水源と関係が深い神社で祀られる。
- 神道と仏教の両方に登場
7. 狛犬・獅子(こまいぬ・しし)
- 神社の守護獣
- 狛犬は朝鮮半島経由で伝来し、日本では神の前に配置される魔除け。
- 獅子は仏教の影響も強く、仏の守護獣。
8. 天狐(てんこ)/白狐(びゃっこ)
- 普通の狐とは異なり、霊力を持った神聖な狐。
- 稲荷信仰の深化に伴い、聖獣的扱いに。
- 千本鳥居を越えた「奥の院」などでは白狐が神のように祀られることも。
9. 鯱(しゃちほこ)
- 鯱(魚の姿の獣)は火除けの象徴として城や神社の屋根に飾られる。
- 特に名古屋城の「金の鯱」が有名。
10. 神馬(しんめ)
- 本来は動物だが、神に捧げられる神聖な存在として、「生ける神聖な獣」とされる。
11. 神鹿(しんろく)
- 関連神:春日大明神(武甕槌命)
- 鹿島神宮から春日大社へ神が白鹿に乗って現れたという神話がある。
- 奈良公園の鹿はこの神話に由来し、「神の使い=神鹿」として保護されている。
12. 金鵄(きんし)
- 金色の霊鳥。神武天皇の東征神話に登場。
- 神武天皇の弓に止まり、敵軍を目くらましにしたとされる。
- 近代には「金鵄勲章」の由来にもなった。
- 日本における「瑞兆」の象徴。
13. 土蜘蛛(つちぐも)/大百足(おおむかで)
- 神聖というよりは「妖異なる存在」だが、地方の伝承では山神の化身や神格的存在とされる場合も。
- 鎮めの対象として社を建てて祀られる例あり(例:足柄の大百足伝説)。
14. 蝦蟇(がま/ヒキガエル)
- 象徴:変化・不死・財運
- 信仰:仙人や道教的信仰と関連(日本では一部の神社や修験者に)
- 例:ガマの油売りなどの口上に登場
15. 烏天狗(からすてんぐ)
- 上記の天狗の亜種で、カラスのような顔をした霊獣的存在。
- 八咫烏とも混同・融合される場合もあり、「導きの霊獣」として扱われることも。
16. 鵺(ぬえ)
- 猫の顔、虎の脚、蛇の尾、鳥の声を持つという怪異。
- 神聖というより妖異だが、源頼政が退治し、神聖化された地(京都の神社など)で間接的に崇敬対象になっている。
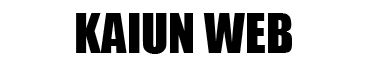






コメント