3. 太陽・光・天空のエネルギーを放つ女神
天照大神(あまてらすおおみかみ)
日本神話における太陽の最高神。世界を照らす光と秩序の源であり、国を治める中心的な神として崇敬されています。
日霊女神(ひるめのかみ)
太陽そのものの霊力を体現する古い女神で、天照と同一視されることもある存在。神聖な日のエネルギーを象徴します。
稚日女尊(わかひるめ)
若々しい太陽の光を象徴する女神。「稚(わか)」の名の通り、再生や新たな始まりのエネルギーを担うとされます。
大日孁貴(おおひるめ)
「太陽の女神」の古称を持つ格の高い神格で、天照大神の原型・別名ともされる存在。大いなる光の働きを司ります。
下照姫(したてるひめ)
その名の通り、地上にまで「照り渡る」光を届ける姫神。柔らかな光や清らかな輝きを象徴し、恋愛や縁結びにも関わる女神です。
天道日女命(あめのみちひめ)
天の道=太陽の通り道を照らす女神。太陽の規則正しい運行と季節の循環を見守る存在とされています。
阿加流比売(あかるひめ)
「明るい」という意味をそのまま体現するような女神。希望や前向きさを象徴する神名で、創作や名付けにも使いやすい響きです。
高比売命(たかひめ)
光と若い生命力に縁深い姫神。地上を照らす明るさと豊穣の両方を司る、情の深い女神として描かれます。
4. 海・雨・川とつながる水の女神
多紀理毘売命(たきりびめ)
宗像三女神の一柱で、霧や潮流など海のダイナミックな側面を象徴する女神。海と陸との境界を守る存在です。
多岐都比売命(たぎつひめ)
同じく宗像三女神の一柱で、潮の満ち引きや海上交通と深い関わりを持つ女神。航海の安全を見守ります。
市杵嶋姫命(いちきしまひめ)
水辺や島の守護神で、のちに弁才天と習合した女神。水の恵みだけでなく、芸能や財宝にもご利益があるとされます。
高龗神(たかおかみ)
山の水源や雨をつかさどる龍神的性格を持つ神。恵みの雨とともに、荒ぶる水の力も制御する存在です。
天之水分神(あめのみくまり)
水の分配・分岐を司る女神で、雨水や水路が必要な場所に行き渡るよう見守る存在。農耕に欠かせない水の調整役です。
八河江比売(やがわえひめ)
「八つの川」に由来する水の女神。豊かな水脈と清らかな川の流れを象徴し、土地の潤いを支えます。
丹生都姫(にうつひめ)
清らかな湧水の地「丹生」を守る女神。水源と土地の両方を守る神格として、浄化や清めとも結びつきます。
豊玉毘売(とよたまびめ)
海神の娘にして龍宮の姫神。海の奥深い豊穣や生命の力を象徴し、母神としても崇敬されます。
速秋津比売(はやあきつひめ)
河口や潮の流れを司る女神で、川と海の境目=水の交通の要となる場所を守る存在です。
5. 山・火山・大地のチカラを宿す女神
石長比売(いわながひめ)
岩のように変わらぬ永遠性を司る女神。長寿や不変の力の象徴として、対になる木花之佐久夜毘売と対比されます。
磐長媛命(いわながひめ)
同じく岩のような長寿を授けるとされる姫神。石長比売と同一視されることも多い神格です。
埴山姫(はにやまひめ)
大地の粘土「埴」を司る女神で、土器作りや建築の土台、土地の安定と結びつきます。ものづくりの基盤を象徴する大地神です。
浅間大神(あさまのおおかみ)
浅間山をはじめとする火山の霊力を司る神。噴火の鎮静と山の恵みを祈る対象として広く信仰されています。
白山比咩神(しらやまひめ)
霊峰・白山の主祭神で、雪解け水の恵みや山の浄化力を司る女神。全国の白山社の中心として崇敬を集めます。
金山姫神(かなやまひめ)
金属や鉱山を管轄する女神。大地の奥に眠る金属資源の霊力を象徴し、採掘や鍛冶の守護神として信じられています。
6. 稲作・食卓・豊穣を支える女神
宇迦之御魂神(うかのみたま)
稲や穀物をつかさどる代表的な食物神。稲荷神として全国に広まり、商売繁盛や衣食住の安定にもご利益があるとされます。
豊受大神(とようけのおおかみ)
食物・農業・衣食住全般を支える大いなる女神。伊勢神宮外宮の主祭神として、国家の「台所」を守る存在です。
大宜都比売(おおげつひめ)
身体から多くの食物を生み出したという神話を持つ食物神。五穀豊穣の源泉そのものを象徴する女神です。
稚産霊神(わくむすび)
「若く産まれ育つ霊」を意味する名を持つ神で、発芽や成長など新しい実りの力を司ります。
神大市姫(かむおおいちひめ)
市場や流通を守る女神。農作物や物資が滞りなく行き渡るよう見守る、市場の守護神として信仰されています。
三穂津姫(みほつひめ)
「三穂」は稲穂の豊かな実りの象徴。稲作の恵みをもたらす農耕の姫神として、五穀豊穣を支えます。
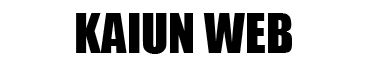






コメント