古くから人々は風の音に、季節を運ぶ優しさと、嵐の激しさの両方を感じ取ってきました。
その見えない力に神性を見出し、人格を与えて祀った文化は世界中に存在します。
日本では風を司る神として「風の神(風神)」が知られ、大和言葉ではシナツヒコ、漢語では風神・風伯・風師と呼ばれます。風にまつわる精霊や妖怪も含めて「風の神」とされることがあり、自然への畏れや敬意がその名に反映されています。
また「風神」という語は、風邪をもたらす疫病神や、江戸期の職能者である風神払い(かぜのかみはらい)を指す場合もあり、多層的な意味を持っています。
世界を見渡せば、春風を運ぶ神、嵐を操る神、旅人を導く風の精など、風の神々の姿は文化ごとに大きく異なります。
ただし、風という見えない力に神秘を見出した点は共通しています。
この記事では、日本から世界各地まで、風の神々・精霊・風にまつわる存在を一覧で紹介し、その特徴と由来をわかりやすくまとめていきます。
出典・参考:Wikipedia 風神
🇯🇵 日本の風の神
1. シナツヒコ(志那都比古神 / しなつひこ)
古事記・日本書紀に登場する、風そのものを司る代表的な日本の風の神。
高天原から吹く風を調整し、穀物を育て、人々の生活の循環を支える存在として描かれる。
2. シナツヒメ(志那都比売神 / しなつひめ)
シナツヒコの女性神格または対になる存在。
豊穣や季節の風を象徴し、柔らかい風・春風のイメージと結び付けられる。
3. 風三郎・風の三郎(かぜのさぶろう)
民間伝承における風の精霊的な存在。
季節の変わり目に強い風を運ぶとされ、地域によっては農業や天候を占う指標として語られる。
4. 風の又三郎(かぜのまたさぶろう)
宮沢賢治の文学作品に登場する象徴的存在。
「風を具現化した少年」のようなイメージで、自然の力や神秘性を表現したキャラクター。
(創作だが、“風の精霊”を象徴するため参考として掲載)
🕉️ 仏教の風の神
5. 風天(ふうてん / Vāyu・Vāta)
仏教の天部の一尊で、十二天の一柱。
インド神話の風神ヴァーユ(Vāyu)・ヴァータ(Vāta)が起源で、
バラモン教から仏教へ取り込まれた。
風を象徴し、疾風・呼吸・生命エネルギー(プラーナ)の働きを司る。
寺院では守護神として祀られ、災害を払い、僧侶の修行を守護するとされる。
🇨🇳 中国の風の神
1. 飛廉(ひれん / フェイリェン)
中国神話における主要な風神で、鹿の身体に鳥の頭、蛇の尾を持つとされる神獣。
「風を呼ぶ獣」として戦いや災害・天候を左右する力を持つ。
2. 箕伯(きはく / ジー・ボー)
古代中国の伝承に登場する風を司る神格。
「箕星(きせい)」という星宿と関連付けられ、風向きや季節の風を支配するとされた。
3. 風伯(ふうはく / フォンボー)
中国で一般的に「風の神」を指す名称。
人の姿・老人の姿など多様に描かれ、地域ごとに伝承が異なる。農業に重要な風を運ぶ存在。
4. 風師(ふうし / フォンシー)
風伯とほぼ同義で、風を調整する役目の天官。
天帝の命を受けて気候を司り、雨師(雨を司る神)と対になる。
インドの風神とその神話
インド神話(バラモン教〜ヒンドゥー教)には、日常の風・暴風雨・大気のエネルギー・破壊と再生をもたらす風など、多面的な“風”を司る神々が存在します。ここでは、主要な風の神々とその背景をわかりやすく整理して紹介します。
1. ヴァーユ(Vāyu)/ヴァータ(Vāta)
日常の風を司るインドの代表的な風神
ヴァーユは、サンスクリット語で「風」を意味する名を持つ、インド最古層の風神です。
同じく風を象徴するヴァータ(Vāta)とはほぼ同一視され、両者ともアーリア人が最古の時代から崇拝した神とされています。
特徴
- 日常の風・呼吸・大気(プラーナ)を象徴
- 『リグ・ヴェーダ』では英雄神インドラと並ぶ重要神
- 大気=生命力として重視され、宇宙の成り立ちとも深く結びつく
- ヴァーユのほうがやや「人格的・神格的」に描かれる傾向
仏教との関係
ヴァーユ/ヴァータはバラモン教から仏教に取り入れられ、
のちの 仏教・十二天の一尊「風天(ふうてん)」の起源となった。
2. マルト神群(Maruts)
暴風雨を司る古代の独立した神々
マルト神群は、インド神話の中でも最古層に属する暴風雨を司る神々の集団。
嵐や激しい風を象徴し、若く勇猛な戦士のような姿で描かれることが多い。
特徴
- 暴風雨・雷・嵐の勢いを神格化した存在
- 英雄神インドラと共に讃えられる場面が多い
- 『リグ・ヴェーダ』では多数の讃歌が捧げられるほど重要
- 集団で行動し、天を駆け、激しく吠えるように嵐を起こすイメージ
信仰上の位置づけ
独立した神群だが、インドラと共に語られることが多いため
「インドラの随伴神」として知られるようになった。
3. ルドラ(Rudra) ― 暴風神からシヴァ神への原形
激しい暴風と“生まれ変わり”を司る神
ルドラは「咆哮者」を意味し、破壊的な暴風、サイクロン、嵐を司る恐るべき神。
暴風がすべてを薙ぎ払った後に訪れる“浄化”や“再生”の感覚も支配する。
特徴
- 暴風・嵐・病気・治癒を司る両面性
- 恐ろしくも慈悲深い「二面性」を持つ
- 『リグ・ヴェーダ』では初期はほとんど謳われないが重要な存在
シヴァ神との関係
後のインド宗教思想(ウパニシャッド以降)で体系化されていく中で、
ルドラの性質は 最高神シヴァ の原形となった。
- シヴァは破壊と再生、ヨーガ、宇宙の循環を象徴する大神
- 「シヴァ(慈悲深い・吉祥な)」という名は
ルドラの穏やかな側面を称えた呼称が起源
つまり、
“恐るべき暴風神ルドラ” → “宇宙的大神シヴァ”
という系譜が成立する。
エジプトの風神とその神話
エジプト神話には、大気・光の風・砂嵐・太陽を支える風など、多様な「風」と関わる神々が存在します。古代エジプトでは風は生命と秩序を支える力であり、また砂漠の暴風のように破壊的な一面も持つと考えられていました。ここでは、エジプト神話に登場する代表的な風の神々を整理して紹介します。
1. シュー(Shu)
大気・光る風を司るエジプト神話の大気神 エジプト九柱の神々の一柱であるシューは、天地創造神アトゥムによって湿気の女神テフヌトと共に生み出された、最初に性別を持った神とされる。 大気を神格化した存在であり、シューは天(ヌト)と地(ゲブ)を引き離し、太陽の道を開く神として重要な役割を担った。
特徴
- 名は「空虚」あるいは「立ち上がる者」を意味し、後に「光」=光る大気の神性へ変化
- 「光る大気」として四つの風と共に天と地の間を循環する存在
- 温和で生命を育む気質を持ち、嵐神セトと対照的
- ヌトをゲブから押し上げて天空を形成し、「太陽の船の守護者」とされた
2. セト(Seth / Set)
砂嵐・破壊・外敵からの守護を司る混沌の神 エジプト九柱の神々に属するセトは、破壊・混乱・砂漠・嵐の象徴でありながら、外敵から国を守る武勇神としても崇められた。 砂嵐を起こす存在として、風神的性格を持つ。また、異国の神ともされ、時代によって評価が大きく変動した神である。
特徴
- 砂漠の風・砂嵐・火・力を象徴する多面的な神
- 外敵には大きな武威を発揮し、軍勢の守護神とされた
- ヒクソス時代にはバアル(カナンの嵐神)と同一視
- ギリシア神話ではテューポーン、キリスト教ではレヴィアタンと同一視される
3. アメン(Amun)
テーベ地方の大気の守護神から、最高神アメン=ラーへ 後に太陽神ラーと習合してエジプト最高神アメン=ラーとなるアメンは、もともとはテーベ地方で信仰された大気の守護神・豊穣神であった。 大気は生命を育む風とも重なる概念であり、アメンは創造力・生殖・豊穣を司る重要な神格として位置づけられた。
特徴
- 本来は「大気の神」であり、生命力の風を象徴
- 中王国時代に太陽神ラーと合体しアメン=ラーとして最高神に上りつめた
- ファラオの王権の正当性を象徴し、国家神として崇拝された
- 創造・豊穣・光・風を司る万能神格へ発展
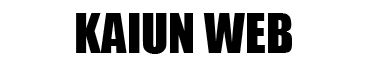






コメント