6. インド神話の女神
インド神話に登場する女神は、学問や芸術を司るサラスヴァティー、富と繁栄をもたらすラクシュミー、戦闘と守護を象徴するドゥルガーなど、きわめて多彩です。特にカーリーのように破壊と再生を同時に体現する女神は、善悪や生死を超えた存在として恐れ敬われました。現代のインドでも女神信仰は根強く残り、祭礼や日常の祈りに息づいています。
- サラスヴァティー (Saraswati, सरस्वती)
学問・芸術・音楽の女神。白鳥に乗り、ヴィーナと呼ばれる弦楽器を奏でる姿で描かれます。知恵と調和を授ける存在です。 - ラクシュミー (Lakshmi, लक्ष्मी)
富と繁栄の女神。蓮の花の上に立つ姿で描かれ、幸運と家庭の安泰を象徴します。ヒンドゥー家庭で広く祈られる女神です。 - パールヴァティー (Parvati, पार्वती)
シヴァ神の妻で、愛と献身の象徴。優しい母性を持ちつつも、ドゥルガーやカーリーの姿に変じ戦闘力を発揮する多面的な女神です。 - ドゥルガー (Durga, दुर्गा)
悪を討つ戦闘の女神。獅子や虎に乗り、多くの武器を携えた姿で描かれます。力と守護を象徴し、祭り「ドゥルガー・プージャー」で盛大に祝われます。 - カーリー (Kali, काली)
破壊と再生を体現する恐怖の女神。青黒い肌と首飾りを持ち、邪悪を滅ぼす力の象徴。畏怖と信仰の対象です。 - ガンガー (Ganga, गंगा)
ガンジス川の女神。川そのものを神格化した存在で、清めと命の源を象徴します。インド全土で最も広く崇拝される女神の一柱です。 - ウマ (Uma, उमा)
パールヴァティーの別名で、優しさと献身を象徴する姿。瞑想と家庭的な愛に結びついています。 - ターラー (Tara, तारा)
慈悲と救済を象徴する女神で、特に仏教でも信仰される存在。母性と守護を司り、緑ターラー・白ターラーなど多様な姿があります。 - スリー (Shri, श्री)
ラクシュミーと同一視される繁栄の女神。王権や富を象徴し、ヒンドゥー教において吉祥のシンボルとして祈られます。 - チャームンダー (Chamunda, चामुण्डा)
死と破壊を司る恐怖の女神で、ドゥルガーの化身。悪魔を討伐する力を持ち、恐ろしい姿で表現されます。 - バガラームキー (Bagalamukhi, बगलामुखी)
言葉や敵を封じる力を持つ女神。智慧と呪術に結びつき、勝利を願う祈りの対象となりました。 - アンナプルナ (Annapurna, अन्नपूर्णा)
食物と豊穣を司る女神。食事の恵みを象徴し、飢えを防ぐ存在として家庭で祈られます。 - ラトリー (Ratri, रात्रि)
夜を象徴する女神。闇と安息を司り、時間の循環を象徴する存在として讃えられました。
7. 日本神話の女神
日本神話には、太陽を司るアマテラス、桜と火山の象徴であるコノハナサクヤヒメ、海を治めるトヨタマヒメなど、自然と密接に結びついた女神が数多く登場します。古事記や日本書紀に記された女神たちは、四季や自然現象を象徴すると同時に、皇室や国土の起源とも深く関わっています。神社信仰にも受け継がれ、現代の日本文化にも大きな影響を与え続けています。
- アマテラス (Amaterasu, 天照大神/あまてらすおおみかみ)
太陽を司る最高神で、日本神話の中心的存在。天岩戸に隠れた逸話は有名で、光と秩序を象徴し、皇室の祖神としても崇敬されています。 - コノハナサクヤヒメ (Konohanasakuya-hime, 木花咲耶姫)
桜の花を象徴する女神で、火山との関わりも深い存在。富士山の神としても祀られ、生命の美しさと儚さを表現します。 - イチキシマヒメ (Ichikishima-hime, 市杵島姫命)
水と海を司る女神で、宗像三女神の一柱。後に弁財天と習合し、芸能や財運の女神としても広く信仰されました。 - タゴリヒメ (Tagorihime, 田心姫命)
宗像三女神の一柱で、海と航海の守護者。海の神として漁業や交通の安全を司りました。 - タギリヒメ (Tagitsuhime, 多岐津姫命)
宗像三女神の一柱。水の流れや川を司り、水神として信仰されました。 - トヨタマヒメ (Toyotama-hime, 豊玉姫命)
海神ワタツミの娘で、山幸彦の妻。龍宮に住み、出産にまつわる神話を持つ女神です。 - タマヨリヒメ (Tamayori-hime, 玉依姫命)
トヨタマヒメの妹で、初代天皇神武天皇の母とされる女神。神聖な血統を象徴します。 - ワカヒルメ (Wakahirume, 稚日女尊)
織物の女神で、太陽神アマテラスの妹ともされます。生活と文化の基盤を支える存在でした。 - イザナミ (Izanami, 伊邪那美命)
国生みと神生みを行った母神。死後は黄泉の国を支配し、生と死の境界を象徴する存在となりました。 - イワナガヒメ (Iwanaga-hime, 石長比売)
コノハナサクヤヒメの姉。岩のような永遠性を象徴しますが、醜さゆえにニニギに退けられたため、人の寿命が短くなったと伝えられます。 - アメノウズメ (Ame-no-Uzume, 天鈿女命/あめのうずめのみこと)
芸能と舞の女神。天岩戸神話で舞を踊ってアマテラスを誘い出したことで知られ、芸能の祖神として信仰されました。 - セオリツヒメ (Seoritsuhime, 瀬織津姫)
川の急流を神格化した水の女神。罪や穢れを水に流す祓えの神として『延喜式』祝詞にも登場します。 - トヨウケビメ (Toyouke-hime, 豊受大神/とようけびめのおおかみ)
伊勢神宮外宮の祭神で、食物・衣服を司る女神。アマテラスに供物を捧げる重要な存在です。
8. 中国神話の女神
中国神話には、不老不死を象徴する西王母、月に住む嫦娥、人類を創造した女媧など、壮大な伝承に彩られた女神が登場します。道教や民間信仰とも結びつき、山や川、星といった自然現象と密接に関連しました。中国文化における女神は、単なる神話上の存在ではなく、長寿や家庭の繁栄を願う祈りの対象として現在も語り継がれています。
- 西王母 (Xi Wangmu, 西王母/シーワンムー)
不老不死を司る女神で、昆崙山に住むとされます。仙人たちの守護者であり、長寿と繁栄の象徴です。 - 嫦娥 (Chang’e, 嫦娥/チャンオー)
月の女神。不老不死の薬を飲んで月に昇り、兎とともに暮らす伝説で有名です。中秋節の物語に欠かせない存在です。 - 女媧 (Nüwa, 女媧/ニューウェア)
天地創造と人類創造を行った女神。大洪水の後に天を修復し、人間を粘土から作ったとされます。文化的英雄としても崇敬されています。 - 瑤姫 (Yaoji, 瑤姫/ヤオジー)
山と川を司る女神で、道教や民間伝承に登場。自然の守護者として信仰されました。 - 麻姑 (Magu, 麻姑/マグー)
若さと不老長寿を象徴する仙女。特に道教で信仰され、豊作や幸福の象徴ともされます。 - 九天玄女 (Jiutian Xuannü, 九天玄女/ジウティエンシュアンニュ)
戦いと戦略を授ける女神。伝説では黄帝に軍略を授けたとされ、道教で武神として信仰されました。 - 碧霞元君 (Bixia Yuanjun, 碧霞元君/ビーシアユエンジュン)
泰山に祀られる女神で、山岳信仰の中心。子宝や健康を授ける存在として庶民に広く信仰されています。 - 天妃媽祖 (Mazu, 媽祖/マーズー)
航海の守護女神で、福建・台湾から東南アジアに至るまで広範に信仰されました。漁民や船乗りの守護者です。 - 織女 (Zhinu, 織女/ジーヌー)
七夕伝説で知られる織物の女神。牛飼いの牽牛との恋物語は星の祭りとして今も受け継がれています。
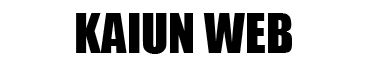






コメント