三吉鬼(みよしおに)
<お酒のお礼に仕事をしてくれる怪力の妖怪>
三吉鬼は、酒好きで怪力の持ち主とされる妖怪です。人里に現れて酒屋で大量の酒を飲んだあと、お礼として夜のうちに大量の薪を置いていったという伝承があります。
また、村の土木工事を一晩で終わらせたという話もあり、秋田県の太平山にある三吉神社の神「三吉様」が姿を変えたものではないかとも言われています。
化狸(ばけだぬき)/妖狸(ようり)/古狸(ふるだぬき)
<化けるのが得意な、親しみ深い動物妖怪>
狸は、古くから人を化かす妖怪として知られており、江戸時代から大正にかけて日本各地で多くの伝承が残されています。新潟の団三郎狸、徳島の金長狸、香川の太三郎狸などが有名です。
こうした狸たちは祠に祀られるほど信仰の対象となっており、中には戦地に出たという「軍隊狸」までいます。
尼彦入道(あまびこにゅうどう)
<豊作や疫病の流行を予言する存在>
尼彦入道は、アマビコ、天日子、海彦とも表記される予言を行う妖怪です。江戸時代後期から明治中期にかけての資料に登場し、熊本県をはじめ各地に伝わっています。
海の中から姿を現し、人間の言葉を使って「豊作になる」「疫病が流行る」といった未来を予言したとされます。また、自分の姿を絵に描いて持っておけば災いを避けられると告げて姿を消すといわれています。
体毛に覆われた姿や三本足、猿のような鳴き声など、見た目にも特徴があり、夜には光って見えることもあると伝えられています。
件(くだん)
<人の姿で災いを告げる、短命な予言獣>
件は、江戸時代から記録のある予言獣で、顔が人間で体が牛という姿をしています。生まれてすぐに人間の言葉を話し、未来の出来事――豊作・凶作・疫病など――を予言したあと、三日ほどで亡くなるとされます。
災いを避ける方法として、自分の姿を絵に描いたり見たりすることを人々に教え、そのまま姿を消すという伝承が多く残っています。アマビコと同様、厄除けの象徴ともいえる存在です。
キジムナー
<ガジュマルの木に宿る、沖縄の赤い妖怪>
キジムナーは、沖縄県に伝わる赤い体と髪を持つ妖怪で、ガジュマルの古木に住むとされています。すき間があれば家にも入り込み、人と関わることがあります。
怒らせると家畜を殺されたり、船を沈められたりすることがありますが、仲良くなると漁を手伝ってくれるなど、頼もしい存在でもあります。名護市の「ひんぶんガジュマル」は、今もキジムナーが住むといわれる有名な場所です。
地域によって姿や性質に違いがあり、黒い姿だったり、ホウキのような形だったという話もあります。
コロボックル(コロポックル)
<姿を見せずに助けてくれるアイヌの小人>
コロボックルは、北海道のアイヌの伝承に登場する小さな人々です。「フキの葉の下にいる人」という意味があり、雨の日にはその葉の下で雨宿りをしていたとされます。
かつてはアイヌの人々と物を交換し合うなど、親しい関係にありましたが、決して自分たちの姿を見せようとはしませんでした。あるとき、無理に姿を見ようとした人間に怒って去り、「トカップチ(水は枯れろ、魚は腐れ)」という呪文を残して姿を消したという伝承もあります。この言葉が十勝地方の名前の由来になったともいわれています。
麒麟獅子(きりんじし)
<魔を祓い、人々に幸福をもたらす伝統舞の獅子>
麒麟獅子は、中国の想像上の動物「麒麟」の頭を持つ獅子舞で、主に鳥取県や兵庫県で信仰されています。神の使いとされ、魔を祓い、人々に福をもたらす存在として知られています。
「猩猩」と呼ばれる役者に導かれて登場し、地域の祭りでは幸福を祈る舞を披露します。単なる伝統芸能ではなく、神聖な力を持つものとして受け入れられてきました。
猩猩(しょうじょう)
<酒を好み、人の言葉を話す赤い妖怪>
猩猩は、顔は人間、体は獣のような姿を持ち、全身が赤い毛に覆われた妖怪です。酒好きとしても知られており、日本各地に伝承があります。
和歌山県の話では、笛の音に心を打たれた猩猩が、礼として釣具を与えたという話があります。その釣具は魚が自然に釣れる不思議な道具だったといいます。
また、愛知県などの秋祭りでは、猩猩の姿をした人形が町を練り歩くことで厄よけとされており、人々にとって親しまれている存在です。
水天狗円光坊(すいてんぐえんこうぼう)
<参拝者を守る川の守護神的天狗>
水天狗円光坊は、山形県の羽黒山に伝わる天狗で、最上川を渡る参拝者の安全を守っていたとされています。かつて羽黒山への参拝は船で行われることが多く、この水天狗が川を渡る人々を見守っていたと伝えられています。
陸路よりも川を通じて多くの信者を導いていたことから、特に重要な存在として崇められてきました。
獏(ばく)
<悪夢を食べてくれる幻の生き物>
獏は、中国から伝わった幻獣で、夢を食べるという性質を持っています。悪夢を見たときに「この夢を獏にあげます」と唱えると、その夢を食べてくれるといわれています。
中国では夢を食べるという伝承はなく、獏の毛皮は病気や災厄を防ぐものとして重宝されていました。日本では室町時代から縁起物として知られ、江戸時代には獏を描いたお守りや枕も使われていました。
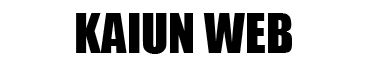






コメント