メソポタミアの風神とその神話
メソポタミア神話(シュメール・アッカド・ウガリット)には、北風・暴風雨・熱風・嵐・天候を司る神々が多く登場します。都市国家ごとに異なる信仰が発展し、激しい嵐や恵みの雨を神格化した独自の「風の神」が形成されました。ここでは、主要な風神を中心に整理して紹介します。
1. エンリル(Enlil)
シュメール神話における風と暴風雨の主神 エンリルはシュメール神話に登場する風・暴風雨・嵐を司る主神であり、都市ニップルの守護神にしてシュメール世界の事実上の最高神とされる。 神々でさえ直接見ることを畏れるほど強大で、彼を祀るニップルは古代メソポタミアの宗教的中心地として長い歴史の中で各国が奪い合う聖地となった。
特徴
- 短慮で激情家だが、暴風雨のように最後には秩序と恵みをもたらす
- 都市滅亡・洪水・疫病など天変地異を自在に引き起こす存在
- 名はシュメール語の en(主)+ lil(風) を意味する
- アッカド語で「ベル(主)」の称号を受け、後代の最高神たちへ継承された
2. ニンリル(Ninlil)
エンリルの妻であり、死後は風の女神となった存在 ニンリルはシュメール神話でエンリルの配偶者として登場し、夫が冥界へ追放された際にその後を追って死に、風の女神となった。 アダパ物語に登場する「南風の女神」はニンリルと考えられ、北風と結び付けられたエンリルに対となる存在である。
特徴
- 「風の女王」として崇められた
- アッカドの悪霊リリートゥと関連し、後のリリス伝説の原型とされる
- 南風を象徴する女性神格として位置づけられる
3. パズズ(Pazuzu)
熱風・疫病・害をもたらす風の魔王 パズズはアッカド神話に登場する風と熱風を司る魔神・悪霊であり、荒れ狂う風と共に熱病を運ぶ災厄の存在とされた。 獣と人間が混在した恐ろしい姿を持ち、蝗害を神格化した存在とも考えられる。
特徴
- 「風の魔王」として恐れられた
- 熱病や災厄を風に乗せて運ぶ存在
- 護符として家庭に置かれることもあり、悪霊除けの役割を持った
4. アダド(Adad / Hadad)
天候・嵐・雷を司るメソポタミアの天候神 アダド(ハダド)は西セム系の嵐の神ハダドを起源とし、メソポタミア広域で嵐・雷・風・雨を操る天候神として信仰された。 多くの地方神と習合し、特にウガリットではバアルと同一視される。
特徴
- 嵐・雷・風・雨を自在に操る天候神
- 農耕に不可欠な慈雨をもたらす存在
- 地域ごとに独自の性質が付与されるほど広範囲で崇拝された
5. バアル(Ba‘al)
カナン地域を中心に広がった嵐と豊穣の神 バアルはウガリット神話やカナン地域で広く崇拝された嵐の神・豊穣神。 名は北西セム語で b‘l(主・主人) を意味し、古代オリエント世界で高位の神として扱われた。
特徴
- 嵐・雨・風を支配し、農耕を司る豊穣神
- 古代オリエント世界の主要神格の一つとして崇拝
- 後世、キリスト教文化圏ではベルゼブブなどの“悪魔”へ貶められた
ギリシアの風神とその神話
ギリシア神話には、暴風・嵐・季節風・四方の風を司る神々が登場します。太古の怪物が生む荒々しい風から、季節や方角を表す規則的な風まで、多面的な「風の神々」が体系的に存在しました。ここでは、代表的な風神であるテューポーン、アネモイ、そしてローマ神話に引き継がれたウェンティを紹介します。
1. テューポーン(Typhon)
ギリシア神話最大の怪物にして、「暴風の源」とされる存在 テューポーンはギリシア神話に登場する太古の巨人神で、神話体系の中で最大最強の怪物とされる。その名は「旋風」を意味するギリシア語 “τύφων (typhon)” が由来で、語源を遡るとインド・ヨーロッパ祖語の「埃・煙」を表す dʰewh₂- に行き着く。 英語の “typhoon(台風)” の語源の一部とされるほど、風や嵐と深い関わりを持つ。
特徴
- 不死の怪女エキドナを妻とし、ケルベロスなど無数の怪物の父となる
- 巨大な身体に百の蛇の頭を持ち、火炎を吐き、翼を持つ姿で描かれる
- 暴風・炎・蛇・火山噴火など、荒々しい自然現象を神格化した存在
- 暴風や乱気流など、不規則で危険な風を生み出したとされる
ゼウスとの戦い テューポーンは地母神ガイアの怒りから生まれ、オリュンポスの神々に戦いを挑む。最高神ゼウスと激しい死闘を繰り広げ、大地と冥界を揺るがすほどの戦いとなった。 最終的にはゼウスの雷霆によって倒され、シチリア島のエトナ火山の下に封じられたとされる。火山が噴火するのは、テューポーンが今ももがいているためだと伝えられる。
2. アネモイ(Anemoi)
ギリシア神話における四方の風の神々 アネモイはギリシア神話における風の神々の総称で、上位4柱・下位4柱に分類される。上位のアネモイは四方位の風を司り、季節や天候にも密接に関わった。
上位のアネモイ(四方の風)
- ボレアース(Boreas):北風の神。冷たく力強い風をもたらす。
- ゼピュロス(Zephyrus):西風の神。春を告げる優しい風として知られる。
- ノトス(Notus):南風の神。嵐や熱風をもたらす。
- エウロス(Eurus):東風の神。変化をもたらす不安定な風。
下位のアネモイ(アネモイ・テュエライ) 元来は怪物テューポーンが生んだ邪悪で粗暴な嵐の精霊だったが、時代が下るにつれて上位のアネモイと同一視され、次第に習合していった。
3. ウェンティ(Venti)
ローマ神話における風の神々で、アネモイの対応神 ローマ神話では、ギリシアのアネモイに相当する風の神々をウェンティ(ヴェンティ)と呼ぶ。 こちらも上位4柱・下位4柱が存在し、四方位の風を象徴する。
上位のウェンティ(四方の風)
- アクィロー(Aquilo, Aquilon):北風の神
- アウステル(Auster):南風の神
- ファウォーニウス(Favonius):西風の神。穏やかな風=ゼピュロスに相当
- ウルトゥルヌス(Vulturnus):東風の神
下位のウェンティ 起源は下位アネモイと同じく、元は邪悪な嵐の精霊であり、後に風の神々と同一視されていった。
ギリシア神話における八つの風神
ギリシア神話には、ボレアース(北風)、ゼピュロス(西風)、ノトス(南風)、エウロス(東風)といった主要な四方位の風神アネモイに加えて、より細かい方角や性質を表す「八つの風」が存在します。これらは海洋活動・航海・季節の変化と深く関わり、人々は特定の風に名前と性格を与えて畏れ敬いました。ここでは、その代表的な八つの風神を紹介します。
1. アイオロス(Aeolus)
風を統べる管理者としての「風の王」
アイオロスは、ギリシア神話においてすべての風を管理する存在として登場します。彼自身が特定の方角の風というよりも、神々や人間のために、必要に応じて風を解き放ったり封じ込めたりする「風の管理者」として描かれます。ホメロス『オデュッセイア』では、帰路にあるオデュッセウスに順風を与え、その一方で他の風を袋の中に封じて渡したことで知られています。
特徴
- 「風の王」として、あらゆる風を支配・管理する役割を持つ
- 特定の方角ではなく、風全体の統括者として描かれる
- 航海と深く関わり、船乗りにとって吉凶を左右する重要な存在
2. アパルクティアス(Aparctias)
ボレアースと関わる「北寄りの冷たい風」
アパルクティアスは、ギリシアの風の体系において北寄りの冷たい風として位置づけられます。しばしば北風ボレアースの一種・変種とみなされ、厳しい寒気や冬の気候を連想させる風として恐れられました。
特徴
- 北寄りの方角から吹く冷涼〜寒冷な風とされる
- ボレアースと近い性質を持ち、冬や荒れた天候の象徴
- 山岳地帯や海上における危険な強風として意識された
3. アフェリオテス(Apheliotes)
東南寄りの穏やかな風
アフェリオテスは、主に東南方向から吹く風として説明されることが多く、比較的穏やかで温暖な風と結び付けられます。農耕や季節の変わり目において、空気の変化を告げる風として捉えられました。
特徴
- 東南寄りの柔らかい風を象徴する
- 雨や湿気を運ぶ風として解釈されることもある
- 激しい嵐ではなく、移ろいゆく天候の変化のサインとなる風
4. アルゲステス(Argestes)
西北寄りの乾いた風
アルゲステスは、西北寄りから吹く乾いた風とされます。しばしば天候を晴れに向かわせる風と考えられ、雨雲を追い払う清々しい風として語られることもあります。
特徴
- 西北寄りの風で、乾燥した空気を運ぶとされる
- 雨雲や湿った空気を吹き飛ばす役割を担う風
- 航海や農耕において「天候の変わり目」を知らせる風として意識された
5. カイキアス(Caicias)
北東風を司る風神
カイキアスは、ギリシア神話における北東の風を象徴する神格です。しばしば冷たく不安定な天候をもたらす風とされ、曇りや雨、荒れ模様の天気と結び付けられました。
特徴
- 北東方向から吹く風を神格化した存在
- 曇天や雨を運びやすい、どんよりとした風とされる
- 主要アネモイのボレアースとエウロスの中間に位置する性質を持つ
6. エウロノトゥス(Euronotus)
東南寄りの湿った風
エウロノトゥスは、東と南の中間から吹く風として位置づけられ、しばしば湿気や雨を運ぶ風とされます。エウロス(東風)とノトス(南風)の中間的性格を持った風神です。
特徴
- 東南寄りから吹く風で、湿った空気や雨を運ぶ
- エウロスとノトスの性質を併せ持つ中間的な風
- 季節の変わり目に強く吹く、不安定な天候と関連する
7. リプス(Lips)
南西風を司る風神
リプスは、ギリシアの風の体系において南西の風を司る神です。海上では特に重要視され、しばしば航路を左右する強い風として恐れられたり、逆に順風として歓迎されたりしました。
特徴
- 南西方向から吹く風を人格化した神
- 航海に大きな影響を与える風として恐れられた
- 湿り気を帯びた暖かい風で、天候の崩れを予兆することもある
8. スケイロン(Skeiron)
北西風・冷たく強い風の神
スケイロンは、北西方向から吹く風を象徴する風神で、しばしば粗暴で冷たい風として恐れられました。アテナイの「風の塔」に刻まれたレリーフでも、スケイロンは一つの方角の風として表現されています。
特徴
- 北西から吹く強く冷たい風とされる
- 海上や海岸線における荒天・荒波の原因と恐れられた
- ボレアース系の冷たい風の一種として扱われることもある
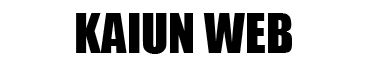






コメント