【物にまつわる迷信】身の回りの道具に宿る“言い伝え”の力
日常で何気なく使っている物にも、昔から多くの迷信や言い伝えが残されています。これらは単なる迷信に見えても、安全・礼儀・しつけなどに根ざした先人の知恵ともいえるものです。
鏡にまつわる不思議な迷信
- 落ちている鏡や櫛は拾ってはいけない
→ 「持ち主の執念がこもっているから」とされ、悪い運を引き寄せるとされました。 - 鏡を上向きにして置かない
→ 「おばけが映る」「親が恥をかく」「ブサイクになる」と言われた地域も。 - 合わせ鏡は縁起が悪い
→ 特に「13番目の顔が死後の自分の姿」という言い伝えもあり、恐れられていました。 - 鏡を伏せておくのは礼儀
→ 鏡は神聖な存在とされ、神道とも深く関わっています。
箸と食器にまつわる迷信
- 貰い箸(箸から箸へ物を渡す)は縁起が悪い
→ 葬儀の際に遺骨を拾う動作を連想させるため、タブーとされます。 - 箸を捨てると貧乏になる/箸が折れると不吉
→ 物を大切にする心を育てるための教えです。 - 本を踏むと罰が当たる/本を粗末にするとバカになる
→ 知識を大切にする気持ちを表したもの。学ぶ姿勢の大切さが込められています。
枕や寝具にまつわる迷信
- 枕を踏むと体に悪い
→ 「足が曲がる」「頭が痛くなる」などと言われ、敬うべきものとされました。 - 枕には魂が宿る
→ 昔は寝ている間に魂が抜けると信じられていたため、枕を粗末に扱うのは禁物でした。 - 枕を3回叩くと良い夢が見られる
→ 就寝前のちょっとした儀式として、穏やかな眠りを願う気持ちが込められています。
その他の物に関する迷信いろいろ
- ざるや洗面器をかぶると背が伸びない
→ 子どものいたずら防止や成長祈願の意図があったのかもしれません。 - 机の上に座ると尻尾が生える
→ しつけや礼儀のための言い回しとして、家庭で語られていました。 - ハサミをまたぐと“切り傷”を負う
→ 道具に宿る神様を怒らせる、という教え。 - 箒にまたがると難産になる(魔女の真似)
→ 西洋から伝わった迷信の一例です。 - 枕を三回叩いて寝ると、良い夢を見る
→ おまじないとして今も楽しまれている迷信です。
【神仏にまつわる迷信】見えない力を敬う、暮らしの知恵
日本では古来より、神仏を敬い、タブーを守ることで災いを避けるという考え方がありました。山・海・道具・方角など、あらゆるものに神が宿ると信じられ、そこから数々の迷信が生まれました。
方位の神を恐れる「金神(こんじん)七殺」
- 金神のいる方位を侵すと七人死ぬ
→ 陰陽道に基づく迷信で、「金神(こんじん)」という神がいる方角への引っ越しや工事などを行うと、災いが起こると信じられていました。方災除けとして祈祷や回避策がとられることもあります。
海の神様にまつわる迷信
- 金属類を海に落とすと大漁が望めなくなる
→ 海の神様は「金気(かなけ)」を嫌うとされ、包丁やハサミを落とすとそのままではダメ。木で形を作り、神棚に供えて謝罪することで災いを避ける風習もあります。 - 「ヘビ」と「サル」は海では禁句
→ これらの動物は海の神様に嫌われており、口にすると不漁になるという迷信もあります。 - 水死体=恵比寿様とされる地域も
→ 港にある恵比寿神社では、海の恵みを祈るとともに、海で命を落とした人々への供養の意味も込められているとされます。
神聖な存在を「見てはいけない」
- お守り袋の中を見てはいけない
→ 神様を直接見るのは不敬とされ、「目が潰れる」とまで言われてきました。神仏に対する畏れを象徴する教えです。
山の神様の不思議な存在感
- 山で「おーい」と呼びかけられても返事をしてはいけない
→ これは山の神に連れて行かれるという迷信。実際には、遭難時に山彦や捜索者の声と混同しないための知恵とも考えられます。
道具にも神様が宿る
- ハサミをまたぐと、ハサミの神様が怒って切り傷を負う
→ 危険な道具への注意喚起として、神様という形で子どもに伝えられた迷信です。ハサミだけでなく、火・包丁なども“神様”が宿るとされてきました。
【妖怪にまつわる迷信】見えない世界との境界線
日本各地には、不思議な存在“妖怪”にまつわる迷信が語り継がれてきました。
自然や日常の中に潜む「見えない力」への畏れや、子どもへのしつけ、暮らしの知恵が形を変えたものでもあります。
お盆に水辺で泳ぐと引きずり込まれる
- お盆に川や海で泳ぐと「猿候(えんこう)」に引かれる
→ 四国地方では、猿候(えんこう)という妖怪が山と川を行き来し、水辺に近づいた子どもを水中に引き込むと言われています。
両腕が背中の中で繋がっており、片腕を縮めてもう一方で足を引っ張るという特徴は、河童とも共通しています。 - 飴をなめながらお風呂に入ると河童に引き込まれる
→ 甘いものは妖怪を呼び寄せるという考え方もあり、「入浴中は行儀よく」という戒めの意味も込められています。
暮らしの中にひそむ妖怪の気配
- 12月8日には「一つ目小僧」が来る
→ この日に履物を外に出しておくと、一つ目小僧がハンコを押して行くという迷信があります。
対策として、ザルを玄関に出しておくと魔除けになるとも言われました。 - 鏡を上向きに置くとオバケが写る
→ 鏡は“あの世とこの世をつなぐ道具”と考えられ、手鏡などは使用後に伏せておくのがよいとされていました。 - 夕方の呼びかけで「もし?」だけはNG
→ 「もし?」の一言だけで声をかけると、妖怪と間違われるという迷信も。
かならず「もしもし?」と二言で話しかけるのが礼儀とされたようです。
不思議な現象と結びつく迷信
- 菜箸で食べると「口裂け女」が生まれる(女の子限定)
→ 女性が菜箸で直接食べると、口裂け女になるという怖い迷信。正しい食事作法を守らせるための言い伝えかもしれません。 - 幽霊船は“指の隙間”や“股の間”から見ると正体が分かる
→ 正体のわからないものに対して“間接的に見ることで真実が見える”という考え方は、昔から多くの地方に伝わっています。 - 九十九神(つくもがみ)も迷信の一種?
→ 長年使われた道具には魂が宿るとされ、粗末に扱うと妖怪になる――これが“九十九神”の伝承です。物を大切にする心の表れでもあります。
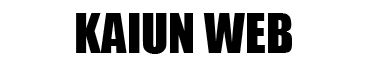






コメント