【植物の迷信】昔から伝わる自然への畏敬と暮らしの知恵
私たちの身近にある植物には、昔から多くの迷信や言い伝えが存在しています。その多くは自然の力や死生観、家の安全を守る願いから生まれたもの。今回は、日本で語り継がれてきた植物にまつわる迷信を紹介します。
彼岸花を摘むと火事になる?
- 彼岸花は「火事花」や「地獄花」とも呼ばれ、不吉な印象をもたれることがあります。
- 実際には有毒植物であるため、触らないようにという安全上の注意が迷信になったとも考えられています。
- 茶碗が割れるという迷信もある「茶碗花(待宵草の一種)」と同様、家庭の器を大事にする気持ちの表れかもしれません。
枇杷(ビワ)の木は庭に植えてはいけない?
- 「庭にビワの木を植えると病人が絶えない」「気が狂う人が出る」という迷信は全国各地で語られています。
- ビワは薬効のある植物とされる一方、「病人が頼って集まってくる=不吉」とみなされた背景があるようです。
- また、墓地や寺に多く植えられる木であることから、死との結びつきが強く、家に植えることを避ける習慣が生まれたとされています。
- 花が「ポトリ」と落ちる様子が、人の首が落ちる様に見えるとして、椿とともに忌み嫌われることもあります。
庭木が屋根を越えると不吉?
- 「庭木が屋根より高くなると家が傾く」「人が死ぬ」などの言い伝えがあります。
- 実際には、大木になると根が家の基礎に影響したり、倒木・落雷のリスクがあるため、実用的な戒めでもあります。
- また、日当たりや風通しの悪化、手入れの手間が増えることなども含め、「屋根より高い庭木はよくない」とされたのかもしれません。
庭木の切り株や井戸は埋めてはいけない?
- 「木を切った後の根をそのまま埋めると良くない」「井戸を埋めるときは竹の節を抜いて道を作る」などの言い伝えは、自然の気(エネルギー)や霊的な通路を断たないようにするという考え方に基づいています。
植物を贈る時のタブー|鉢植えと病人
- 「鉢植えを病人に贈ると寝付く=根付く(ねづく)」という語呂合わせから、鉢植えはお見舞いに不向きとされることがあります。
- また、椿の花も病人への贈り物には避けられます。花が首が落ちるように丸ごと落ちるため、縁起が悪いとされています。
神社の木の葉で霊が見える?
- 神社に生える木の葉でまぶたをこすると、霊が見えるようになるという不思議な言い伝えも。これは、神聖な場所に宿る霊的な力に由来するものと考えられています。
竹・笹の花が咲くと災厄の兆し?
- 非常にまれに咲く竹の花は、「災いの前兆」「凶作の兆し」とされてきました。
- 竹は何十年に一度、花を咲かせると一斉に枯れる性質があり、過去には竹の花の年に災害や飢饉が起こったという記録も。
- 大量に実をつけた年はネズミが増え、農作物が被害を受けることから、竹の開花と災厄が結びついたのではないかと言われています。
- また、「枯れる前に花を咲かせる」という習性があるため、寿命を迎える兆し=不吉という認識にもつながっているようです。
【人物と身体にまつわる迷信】昔ながらの暮らしの知恵と教訓
迷信は、科学では説明しきれない人々の想像力や、伝統的な価値観から生まれた“心の習慣”とも言えるもの。
新品は年長者から使うと長持ちする?
- 「新品の布団や道具は、まず年寄りに使ってもらうと長持ちする」という迷信があります。
- 長寿と知恵の象徴である年配者が使うことで、物にも良い気が宿ると考えられていたようです。
睡眠中の人に話しかけてはいけない?
- 寝ている人に話しかけると「魂が戻ってこられなくなる」とされる迷信。
- 睡眠中は“魂が身体を離れている”と信じられており、外からの刺激で混乱を招くとされてきました。
- 実際、寝言に反応すると脳が混乱するという説もあり、ある意味で理にかなっている部分もあります。
寝ている人をまたぐと不吉?
- 「寝ている人をまたぐと身長が伸びない」「不幸になる」「死んでしまう」など、またぐ行為を禁じる言い伝えは全国にあります。
- これは人の尊厳を重んじる精神や、身体への敬意を表す文化から来ているとも考えられます。
猫が死体をまたぐと…
- 「死体を猫がまたぐと魂が戻ってくる」「化けて出る」といった迷信は、死と動物の神秘的な関係性を表しています。
- 日本では猫に霊的な力があると信じられ、死体の上に刃物を置くなどのおまじないが行われてきました。
- これには、病気の媒介者であるノミなどへの警戒も含まれていたとされます。
水死体にまつわる漁師の言い伝え
- 古くは、水死体を発見すると「大漁の前触れ」とされ、丁寧に扱うと海の神様に近づけるという迷信がありました。
- 船に遺体を上げる際の手順や、海辺に火を焚いて“導く”儀式なども存在します。
- 水死体を「恵比寿さま」と呼ぶ地域もあり、信仰と死者への敬意が混在する文化が見られます。
へそのゴマを掃除するとお腹が痛くなる?
- 「へそのゴマ(汚れ)を取るとお腹が痛くなる」という迷信は、未熟な衛生環境を背景に生まれた教訓と考えられます。
- へその皮膚は薄く、強く触ると炎症を起こす可能性も。子どもに対する注意喚起の意味合いが強いでしょう。
しゃっくりを止める迷信あれこれ
- 箸を湯のみに乗せてお茶を飲む、十字型に置いて飲む、向こう側から飲むなど多くのバリエーションがあります。
- 実際、しゃっくり(横隔膜のけいれん)には姿勢や呼吸の変化が効果的とされており、迷信が理にかなっていることも。
つむじにまつわる迷信
- つむじが二つある人は「ひねくれ者」「大物になる」「王者の相」など、良くも悪くも目立つ人物になるという言い伝えがあります。
- また「つむじを押すと下痢になる」という迷信も。これは神経の集中部位を意識しての注意喚起かもしれません。
夜に爪を切ると不吉?
- 「夜爪(よづめ)をすると親の死に目に会えない」という迷信は非常に有名です。
- 由来には複数あり、1つは夜に灯りが弱く深爪する危険を避けるため。もう1つは「夜詰(よづめ)」=夜勤の武士の語呂から。
- また「世を詰める(寿命を縮める)」という語呂合わせも影響しているとされます。
親指を隠す理由
- 墓地の前や霊柩車を見たときに親指を隠す風習は、「親の死に目に会えない」という迷信に由来します。
- 同様に、弔事の場では小指を隠さないと我が子に災いがあるという地域もあり、親子の命を守るまじないとして行われています。
髪・爪・指にまつわる迷信
- 落ちた髪を他人が拾うと「失恋する」などの迷信も。
- 高知県の「いざなぎ流」では人の爪が呪物として扱われるなど、身体の一部が持つ霊的な力への信仰が見られます。
- 「人のポケットに手を入れると家が火事になる」など、人との境界を越えることを禁じる迷信もあります。
梅干しや食べ物にも呪的な力が?
- 「梅干しがカビると死人が出る」「食べ物を粗末にすると目が潰れる」など、家庭内の変化と死の兆しを結びつける迷信も数多く存在します。
- 食べ物への敬意を表す道徳的な背景も見逃せません。
足のしびれ・背中への迷信
- 足のしびれを治すための民間療法として、「指に唾をつけて眉間を撫でる」「もくさいと唱えて撫でる」などがあります。
- 背中に線を引くと不吉という迷信もあり、これは霊的な影響や呪いを恐れる文化が反映されています。
【行動にまつわる迷信】踏んではいけない、またいではいけない理由とは?
日々の何気ない行動の中にも、「それ、してはいけない」と言われる不思議なタブーが存在します。生活習慣や家の中のしぐさにまつわる昔ながらの迷信を紹介します。
枕は特別な存在?|座る・踏むのはNG
- 枕には「魂が宿る」とされ、座ったり踏んだりすると頭痛が起きる・足が曲がるなどの迷信があります。
- 大切な寝具であること、そして「頭をのせるもの」という神聖な役割があることから、敬意をもって扱われてきたようです。
敷居や玄関の仕切りは踏んではいけない
- 「敷居を踏むと足がなえる」「家が滅びる」といった言い伝えがあります。
- 敷居は家の境界であり、神聖な結界ともされてきた部分。家を大切にする心の表れとも言えるでしょう。
人をまたぐとどうなる?
- 「寝ている人をまたぐと背が縮む」「人をまたぐと偉くなれない」などの迷信があります。
- これは人を軽んじる行為への戒めと考えられています。また、魔除けや霊的な境界をまたぐことを避けるという信仰にも通じます。
はさみや本をまたぐとバチが当たる?
- 「はさみをまたぐとケガをする」「本を踏むとバチが当たる」といった迷信は、道具や学問に対する敬意を表しています。
- 特にはさみは「神様が宿る道具」ともされ、軽々しく扱うことへの戒めでもあります。
落ちている鏡や櫛は拾ってはいけない?
- 「落ちた鏡や櫛には持ち主の執念がこもっているため拾ってはいけない」という言い伝えがあります。
- 特に櫛=“苦”と“死”に通じることから、贈り物や拾得物としては避けられることも。
- 櫛を拾うときは一度足で踏んで「因縁を断ち切る」とするおまじないも伝えられています。
掃除や排泄にも意外な迷信が
- 「掃除でごみを窓から直接外に出すと金運も逃げる」など、運気にまつわる行動への注意も多くあります。
- また「トイレに裸で入ると、できものだらけの子が生まれる」などの迷信は、羞恥心や慎みを教えるためのものとも考えられます。
「またぐ」にまつわる西洋の迷信
- 魔女の象徴ともされる箒を「またぐと難産になる」というのは、西洋の迷信です。
- 箒は古くから女性の道具とされてきたため、女性の身体や出産に関わる禁忌と結びついていたようです。
食後すぐ寝ると「牛になる」?
- 有名な迷信のひとつですが、これは「食後はしばらく休んでから横になった方がよい」という健康上の教訓でもあります。
- 牛は反芻動物で、寝ながら食べ物を戻す姿がモデルになったとも言われています。
その他のユニークな迷信
- 「机の上に座ると尻尾が生える」「洗面器やざるを頭にかぶると背が伸びなくなる」など、子どもへのしつけに使われたユーモラスな迷信も多数。
- 遊び半分の行動を戒めるための、親世代からのやさしい警告とも言えます。
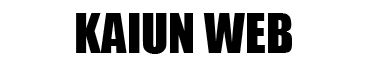






コメント